ビジネスプランコンテスト受賞者の声
これまで開催の「みたかビジネスプランコンテスト」において、優れたプランで受賞された方々をご紹介いたします。
なお、今回開催の「みたか創業・成長支援アワード」は、これまでのコンテストとは異なる趣旨・構成で実施しています。
両者に直接的な関連はございませんので、あらかじめご留意ください。
2024年度 ビジネス部門
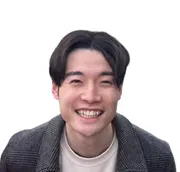
最優秀賞
わずかな時間で最適な間取りを自動生成
複数の建築会社に見積もり依頼ができるサービス
間取りの窓口
野口 雄人 さん
兄の家の設計を頼まれて
家を建てることは、多くの人にとって夢が膨らむ一大プロジェクトです。ある複数の調査によると 注文住宅を新築された人が最もこだわったのが「間取り」だそうです(*注)。
野口さんが手がける『間取りの窓口』は、AIを活用した「自動間取り生成」によって、家を建てる人(施主)と工務店・ハウスメーカーなどの建築会社とをつなぐマッチングプラットフォーム。施主は専門的な知識がなくても、土地の情報と希望の部屋数や何階建てかを入力するだけで、わずかな時間で最適な間取りを作成することができます。そして、それらを複数の建築会社に一括して送ることで見積もりの依頼・比較ができる一方、建築会社は設計業務の効率化と、潜在的な顧客のデータ収集を行うことが可能となります。
野口さんがこのアイデアを思いついたのは、東京大学で建築を学んでいるとき、家の新築を予定していた6歳上のお兄さんから、「間取りを考えてほしい」と依頼されたことがきっかけでした。
「当時大学3年生だった私が全力で案を作っても、却下される日々。打ち合わせは十数回にも及びました。そんなとき、兄が自分で希望の案を出してきたのですが、それがとても素晴らしい案だったのです。このとき、施主が自ら間取りを考えることができるツールがあればと閃きました」
「形にして、届ける」諦めない強い思いが原動力に
野口さんは、数々の開発経験のある東京大学大学院情報理工学系研究科の早稲田風太さんに依頼し、4人の精鋭によるエンジニアチームを作り、開発に着手します。
当初は建築会社に設計の効率化ツールとしてこのサービスをサブスク的に使ってもらおうとしていました。しかし、営業のハードルが高いことに気づきます。
実は野口さんはすでに中古品販売のビジネス経験があります。扱っていたのは製図版や平行定規など、設計を学ぶ際に必要なアイテム。高価でありながら実際に使う頻度や期間が限られているもので、需要を見込んで始めたビジネスでした。その頃出会ったコンサルティングの人たちに間取りの自動生成ビジネスの可能性を聞くうち、建築会社から顧客紹介手数料をもらうという仲介サービスであれば可能性が広がるのではないかと確信します。「自分の中でモチベーションになっているのが、『ここまで努力してきたものを形にして、人に届けたい。諦めてしまったらもったいない』という気持ちです。成功させて、エンジニアチームに報いたい気持ちもありました。アドバイスを受けて、面白いアイデアだと言ってもらえたことが次に進むステップになりました」。
日々進歩し、ライバルが増えているAI市場ですが、「真似しにくい技術を持っているのが大きな強みです。ここ1,2年のあいだに一気に自分たちのシェアを獲得することによって、他社の入り込む隙間を少しでもなくしていくという戦略を持っています」と自信を覗かせます。
自分の思い描いたものを納得の行くまで作る楽しさを
2025年3月の法人化に向け忙しい毎日を送っている野口さん。
サービスを公開して2日後には利用者が100人を超え、以降、毎週数十人単位で新たな顧客が増えているそうです。今後はアルゴリズムの実装を進め、施主ユーザーと建築会社との契約数をさらに増やしていきたいと意気込みます。
「住宅は一生のうち、一番大きな買い物。自分の思い通りにいかないと失望も大きくなってしまいます。何十パターンも、何百パターンも、納得のいくまで間取り作りを試してみてください。頭に思い描いたイメージを1分で形にすることができるという楽しさを感じてもらえたら嬉しいです」
*注
LIFULL HOME’S 経験者500人に聞く家づくりでこだわったこと 第一位「間取り」(2023年1月)
石原工務店株式会社 注文住宅購入者の実態調査(2024年11月)注文住宅のこだわりポイント 「間取り・プラン」が64%で最多に

優秀賞
JR中央線コミュニティデザイン賞
果物の「健康、美味しさ」成分を効率よく抽出、摂りやすい形で販売
渡邉 幸雄 さん
収穫されない果実や植物の加工品を開発
民家の庭先に植えられている梅や柿、柑橘類。渋味や酸味が強いために食用には適さず、そのまま朽ちてしまうものも少なくありません。渡邉さんはこうした果物に注目し、加工品を開発。3人の医師や管理栄養士からの理論的サポートも得て、長い期間、原液エキス商品、残滓物である果肉を活用したジャム、ドライフルーツ、ナッツやバターなどを組み合わせた商品を開発してきました。「果物や植物の内容物を浸透圧の原理で抽出させ、麹菌により発酵させると、組織を壊すことなく、雑味のない素材そのものの味わいが生まれます。栄養価、保存性、身体への吸収力なども高まります」と、その魅力を語ります。
35年間、大学病院の東洋医学科や整形外科など臨床の現場で、リハビリテーションの仕事に携わってきた渡邉さん。「痛み」のメカニズムに関心を寄せ、「関節運動学」「関節神経学」の考え方から学びを深めるなかで、抗酸化物質を多く含む食べ物の摂取が、痛みや炎症の改善に役立つのではないかと考えるようになりました。
そんなとき、埼玉県秩父在住の方から治療の依頼があり、毎週通っているうちに知人が増え、民家の庭先にある梅や柿、柑橘類の木々の手入れを手伝うように。そして、これら捨てられてしまう運命にあった果物を収穫し、健康的に美味しく食べるための試行錯誤を重ね、自らも身体に取り入れることによって不調を乗り越えてきました。
スーパーフード「梅」を世界へ発信
活動は秩父地方だけでなく、群馬県箕野町や静岡県静岡市の日本平などに広がり、畑でルバーブや赤ビーツなどを栽培するようになり、取り扱い量も増えています。
渡邉さんが特に可能性を感じているのは梅だといいます。
「梅は梅干しなどの形で健康によい食べ物として、古くから親しまれているスーパーフード。『紀州梅効能研究会』という、複数の医科大や病院による研究会があるのですが、梅に含まれるクエン酸や梅リグナン、バニリン、ポリフェノールなどの健康成分についての研究が数多く発表されています」
マルシェでも、ほとんどの人が梅製品に関心を示し、根強いニーズがあるそうです。
渡邉さんはさらに、このように歴史ある優れたものを日本から海外に発信することができたら、と話します。「梅ポンチ(原液エキス)や、果肉を使った加工物は、おそらく世界で通用するはず。世界でも肉・魚・卵などを食べないヴィーガン人口の割合が高いイギリスで受け入れられるのではないかと思っています」
特に、日本の農業は課題も多く、世界市場への進出が必要だろうと考えています。「食料は、人間の生命の維持に欠くことができないものであり、健康で充実した生活の基礎として重要なもの。自給率を向上させるには、身近な食べ物を大切にしていくことが必要だと思っています」
地域資源の活用でコミュニティの活性化など課題解決につなげる
高齢化が進む日本で、今後、ますます健康志向が高まり、身体によい食べ物への関心は広がっていくことでしょう。
その中で、本来であれば捨てられてしまう果物や植物を有効活用した商品の開発は、SDGsの観点からも大切といえます。
現在は製造を外注していますが、今後は都内にポンチを作る清涼飲料水加工所や残滓物を利用した製品を作る菓子製造キッチンを兼ねた工房の設立を視野に入れています。そして、そこから地域コミュニティの活性につながるような活動が出てくることを想定しています。
「都内には、クラフトジンジャージュースやクラフトコーラなどを作るような場所はあまりありません。今後、たとえば若者がオリジナルの飲料水を作りたいと思ったときに、原材料を提供できるような、OEMの仕組みができたらと考えています」
渡邉さんは事業の屋号を「lea Farm」(レア・ファーム)と命名しています。レアとはハワイの言葉で「喜び、幸せ、歓喜」を意味します。3年前に亡くなった愛犬の名前でもあり、商品のパッケージには愛犬のイラストがあしらわれています。
人々に喜びをもたらす農場づくり。渡邉さんの挑戦は続いていきます。
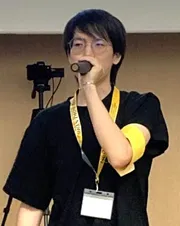
三鷹発ベンチャー賞
地元に愛されるesportsチームをつくる
久間 巧也 さん
世界中で盛んな「eスポーツ」に注目
「eスポーツ(esports)」とは、「エレクトロニック・スポーツ」の略称で、コンピューターゲーム、ビデオゲームを使った対戦競技のことです。インターネットの普及を背景に、2000年代初めに「eスポーツ」ということばが生まれ、フランスや中国、韓国などで大規模な国際大会が開催されるように。日本では2015年に「(一社)日本eスポーツ協会(JeSPA)」、2018年に「(一社)日本eスポーツ連合(JeSU)」が設立され、競技人口が増えつつあります。2022年には市場規模が100億円を突破。2025年は210億円を超えると見られています(JeSU調べ)。
2021年から「てぃ」のネームでeスポーツの活動をしている久間巧也さん。選手としてだけでなく、大会を主催したり、イベントのカメラマンとしても活躍。長く居住する三鷹市を中心とした地元密着のeスポーツチームを誕生させ、地域活性化に繋げられないかと思い立ちました。
リアルのスポーツ少年から eスポーツ選手へ
3歳から水泳を始め、小学生低学年からはサッカーや野球を経験し、高校時代は馬術部に所属していたという久間さん。とくに指導者に恵まれた馬術競技で、技術的にも精神的にも成長することができたと振り返ります。「競技にどう取り組めば持てる力を最大限に発揮できるかを真剣に考えたり、道具を大事にすること、礼儀作法の大切さも学ぶことができました」
大学卒業後、「人を笑顔にする仕事に就きたい」と介護業界へ就職した久間さんは、eスポーツに出会います。任天堂のゲーム「大乱闘スマッシュブラザーズSP(通称:スマブラ)」のオフライン対戦会に参加し「想像をはるかに超える上手い人たちがたくさんいる!」と衝撃を受け、技を磨きました。
競技にかける思い。大会での熱気。選手たちのドラマ……。リアルのスポーツと同じように、人を熱狂させるものがeスポーツにもある。それを多くの人に広めたいと、eスポーツ業界への転職を果たします。
eスポーツのゲームは、それほど体力がなくてもプレイすることが可能であり、年齢差や性差にとらわれることなく、誰もが楽しめることが最大の魅力だと久間さんはいいます。
「たとえば不登校の子どもたちにも体験してもらえると思います。礼儀や思考力などリアルのスポーツ経験から得られたものを子どもたちに伝えていくことができればと思います。また、介護職の経験から、eスポーツのゲームによる介護予防などお年寄りにもアプローチができる。これは自分ならではの強みではないかと思っています」
地域を盛り上げるチームを目指して
「選手を集め、名前を決めてロゴを作ればチームを立ち上げることは可能です。私が実現したいのは人々が交流することができる地域密着のチームです」
モデルとしたのが、江東区亀戸の商業施設「カメイドクロック」を拠点に活動するeスポーツチーム、「カメイドタートルズ」の存在です。
「『カメイドタートルズ』はeスポーツチームとしてスタジオを開設して選手の育成に努めるだけでなく、Minecraft(通称:マイクラ)というゲームを使ってプログラミングの基礎を子どもたちに教えたりと、eスポーツを通じて地域貢献や交流を図っています。地域に特化したeスポーツチームは全国的にもまだ非常に珍しく、三鷹市で多くの人に応援してもらえるチームをつくることができたら、と思っています」
将来は三鷹市内にスタジオを設立し、チーム対抗戦やファンミーティング、子ども向けイベントなどを開催できるようになりたいという久間さん。
強い選手が集まり、チームの実力が上がっていけば、世界にも発信していける、と夢を大きく膨らませています。
2023年度 ビジネス部門

最優秀賞
JR中央線コミュニティデザイン賞
美大生と社会との繋がりを作る『小さな美術館』
坂上 大斗 さん
「美大生の友人の夢」を聞いて火がついた
一般の方に作品を見てもらう機会がなく、夢が潰えてしまうかもしれない美大生の発表の機会と利益の循環を生むプロジェクト『小さな美術館』。若者の活躍とアート文化の繁栄を目指しています。メインはアートレンタル事業。主に飲食店や企業など、作品を借りる施設のオーナーは低額で内装を変えられます。また美大生を応援することでの話題作りや、集客力の向上を提供することを可能にしたプロジェクトです。
このプロジェクトの立ち上げメンバー坂上さんからバトンタッチされ、現在代表を務める矢内鉄朗さんは「美大生の友人が夢を追いかけているのを見て、応援したいと思った」ことが企画のきっかけだったと語ります。
起業家の卵と美大生、互いの凸凹のマッチング
「小さな美術館」のプロジェクトメンバーは、武蔵野大学アントレプレナーシップ学部に通う現役大学生です。「1年間で売上をあげる」という授業課題があり、様々なビジネスアイデアについて議論し合いました。その中で矢内さんは、美大生の友人のことを思い出したそうです。高校生の頃に一緒にサッカーをやっていた仲間で、美大に進んだ友人がアーティストとして活躍するという夢をもって作品を作り続けるのを見て「かっこいいな」と感じたそうです。
自分はサッカーを辞め、夢を失っていたこともあり、「好きなことで稼いでいきたい」と夢を持ち続け作品作りをする美大生の友人が、社会の中で生きにくそうにしている現状を見て、どうにかサポートできないかと考えました。そこで思いついたのが、「ビジネス」と「アート」のマッチングです。「まず、彼らが何に困っているのか知るために、100人くらいの美大生にヒアリングを行いました。美大では表現の仕方は学ぶけれど、仕事やビジネスへの繋げ方は学びません。逆にビジネスを学ぶ私たちと組むことで、お互いの学びが活かしあえるのではないかと思いました。」と語られました。
アートを気軽に楽しめる身近なものに
美大生が作成した作品を購入またはレンタルすることで、施設側がその作品をインテリアの一つとして展示することができるサービスが「小さな美術館」です。「多くのお店や企業でも、実際のアートに触れる機会が少ないという現状があると感じています。美大生が個展を開いても、来るのは美術に興味のある人が殆どです。このサービスを始めることで、普段の生活でアートにあまり関わりがない方でも気軽に作品に触れることができる小さなきっかけを作りたいと思っています。」と、プロジェクトメンバーは語ります。
また、「美大生にとっては、利益の循環だけでなく社会とのつながりを持つことが大切だと感じています。」と語るメンバー。「金銭的な価値よりもっと大切なのは、彼らの作品が多くの人の目に触れて、フィードバックをもらうこと。そして、企業とのコラボレーションなど一緒に企画や仕事をするチャンスを増やすことだと思っています。」
小さな美術館では、すでに名古屋の企業と共同でコンペティション企画なども立ち上げたことがあるそうです。
「実際にアーティストとつながりたくても、企業側から大学生個人へは連絡しにくいと感じます。お互いをいい関係を築きながら繋いでいきたいです。」と語るのは代表メンバーの矢内さん。今後は、アーティストとして登録をした美大生へのフィードバック機能なども充実させていくそうです。学生同士が手を取り合うことで、夢が大きく広がっていく未来が想像できました。

優秀賞
がんの治療から表情を守るがん医療アートメイクを医療の新常識に
一般社団法人
全日本がん脱毛医療アートメイク
石原 穂乃佳 さん
がん医療、アピアランスケアでの「盲点」
二人に一人はがんになると言われる時代。がん治療は進歩していますが、抗がん剤治療の副作用である「眉毛」の脱毛のケアに関しては、医療機関でもほとんど目を向けられていません。この課題を解決するため、石原さんは「一般社団法人全日本がん脱毛医療アートメイク」を立ち上げました。医療アートメイクをアピアランスケアの新基準にすることを目指し、施術ができる環境を整える活動に取り組んでいます。
アピアランスケアとは、医療用語で「外見のケア」のこと。脱毛や皮膚障害など、抗がん剤治療の副作用で現れるさまざまな症状に対し、その人らしく社会生活を送れるよう患者さんをケアすることを指します。治療が始まる前にウィッグなどの準備を案内することもそのひとつです。髪の毛の脱毛は比較的知られていますが、あまり知られていないのが眉毛の脱毛。実はかなりの確率で生じるそうですが、治療前には想像できない患者が多く、アピアランスケアの盲点になっていると石原さんは言います。
治療以外の心理的負担を減らすために
子どもの頃から眉毛が薄いことがコンプレックスだったという石原さんは、学生の時に眉のアートメイクを経験していました。その後、看護師として医療現場で働くようになったころ、法律が変わり、アートメイクが医療行為になったことを耳にします。「自分がかつて困っていたことを、看護師の仕事として解決することができる」と思い、すぐに資格を取得。医療アートメイクアーティストへと転身します。
転機は、あるがん患者さんとの出会いでした。その方は、抗がん剤治療の副作用で眉毛が抜けてきたことが気になり、「自分の顔が変わっていくのが不安。アートメイクを受けたい」と石原さんの元を訪れました。しかし、当時は眉毛が抜けてしまった人への施術に対応する知識がなく、断るしかありませんでした。「それだったら、抗がん剤の治療を受ける前に知りたかった。」と言われ、眉患者にとって眉毛が抜けることはとてもショックが大きいことに初めて気付いたそうです。
一度抜けてしまった眉毛の毛根が完全に戻るまでには長い時間がかかります。石原さんは、抗がん剤治療を受ける前に「医療アートメイク」という選択肢があることを医療現場から発信してもらいたいと考えました。「がんの通院治療をしている方の中には、家事・育児・仕事など社会と関わりながら生活している方も多いです。外見が変わることへの不安を軽くして、心理的負担を減らすことは、QOL(クオリティ・オブ・ライフ)の向上に大きく関わってくると思います。」
全国の看護師とチーム連携して認知を広めたい
日本では「アートメイク」という言葉そのものの認知度が低く、さらに医療行為であることも知られていない現状があります。MRIに対応可能なアートメイクがあることもあまり知られていません。アートメイクに対する正しい情報を届けるため、石原さんは「おまもりアートメイク」というホームページを立ち上げました。現在はSNSなどをとおして、がん患者さん向けに発信をしています。
また、アートメイクは施術料も高価であり、価格を下げて提供したくても病院側の協力がないと難しいと言います。「がん患者は全国にたくさんいます。私個人の力で現場に影響を与えることは難しいと考え、起業を決意しました。各都道府県にひとつは施術ができるクリニックがある状況にすることが今後の目標です。」と語る石原さん。そのために石原さんは全国にいるアートメイクの施術者や看護師同士のネットワークを作り、確かな知識と技術を持ったアーティストの「アピアランスケアチーム作り」に動き出しています。チームで連携し、がん専門の病院やクリニックにパンフレットをおいてもらうなど、協賛・協力してもらえる病院を増やしていくことが目標です。「困っている人に技術を届けたい」という石原さんの想いは、現在、福岡・大阪などにも広がり始めています。

三鷹発ベンチャー賞
未来をつなぐ同行援護事業所~音の輪プロジェクト~
DIH Creation合同会社
大江 貴子 さん
ミュージシャンと視覚障害者の出会いから生まれた事業アイデア
「同行援護」とは、視覚障害者の外出時などに付き添いサポートするサービスです。このサービスを利用する方も、同行援護の従事者であるガイドヘルパーも高齢者が多いという現在の状況を踏まえ、若い人も気軽に利用できる新しいスタイルを目指すことが、大江さんの「音の輪プロジェクト」です。若い障害者の活動の範囲が広がることで新たな社会貢献への相乗効果も視野に入れた取り組みです。
ミュージシャンとして活動中の大江さんは、ある視覚障害者との出会いをきっかけに、同行援護のサービスを知りました。その方はこのサービスの利用者で、ガイドヘルパーに依頼をして出かけているということを聞いたのです。「あなたもガイドヘルパーをやってみたら。」と誘われ、ガイドヘルパーの資格を取得。当時はコロナ禍で、ライブなどのミュージシャンとしての活動も難しい状況でした。大江さんは、空き時間にガイドヘルパーとして働きはじめました。
利用者に付き添うことで喜んでもらえるのはもちろん、サポートしたり、食事を共にしたりと、心の距離感も近づきます。人の温かみに触れられる仕事だと感じつつ、ガイドヘルパーを続けました。
助け合いの輪で、みんなが恩恵を受けられる仕組みに
ガイドヘルパーを続ける中で、同行援護サービスの利用者だけでなく、登録している同行援護従事者も高齢化していることに気づきます。同行援護事業のサービスが始まった2011年当初から利用者もガイドヘルパーもそのまま歳を重ねられ、若い視覚障害者はあまりそのサービスを使っていないという現状がありました。若年層にもっと認知を広げる必要性を感じたそうです。
そんな時、大江さんが同行援護をしていた方が突然亡くなるという出来事がありました。人生は何が起きるかわからない、もっと自分の人生を大事にしなくてはいけない。と実感したそうです。この経験が大江さんの心に火をつけ、起業への挑戦につながりました。大江さんは、ミュージシャン活動の中でも、視覚障害者と一緒にライブをするなど積極的に交流をはかっています。「何かを成し遂げたいと思ったら、自分で行動してチャンスを掴んでいく必要がある。でも、視覚障害者は外出するにもハードルがあると思うので、行動を抑制するものを減らしてあげたい。」と語る大江さん。
ガイドヘルパーも可能な限り高時給で提供する仕組みにしたいと大江さんは語ります。「ミュージシャンなどを目指す方には、活動費を稼ぐためにアルバイトで苦労する人も多いです。そのような若者たちに、ガイドヘルパーという仕事を紹介して、お金のために働くのではなく、人のためになる仕事で収入を得る経験をして欲しい。人間味のある仕事が、成長の糧になるのではないかと考えました。
そういった想いから生まれたのが「音の輪プロジェクト」。音から情報を得る視覚障害者と、ミュージシャンやアーティストを目指す若者をつないで、いい循環を生み出したいという意図が込められています。
SNSツールやアプリ開発で若者にも波及を
「自分だけで動いていても大きなことはできない。どうやって多くの人を巻き込んでいくかが今後の課題です。」という大江さん。まずは三鷹で1店舗成功例を作り、その後はフランチャイズ化して関東での事業展開を目指しています。また、いずれはアプリ開発をして、今はほぼ人力で行っているガイドヘルパーの派遣業務を、システム化する構想もあります。「若い人も利用しやすいよう、利用者がスマートフォンからオーダーでき、ガイドヘルパーとすぐマッチングできる仕組みにしたいです。」
利用者とガイドヘルパーのいい出会いを生むことで、新しい循環が生まれる。そんな温かい「音の輪」のビジョンが、大江さんのお話から見えてきました。

三鷹発ベンチャー賞
教室から世界と繋がる!国際的な視野を広げるプロジェクト
Ukulele★Paradise(ウクレレ★パラダイス)
高嶋 尚子 さん
音楽をとおして国際的な視野を身につける教育を
公立小学校の授業にウクレレを導入し、音楽をとおして世界とつながる総合学習を子どもたちに提供することが「Ukulele★Paradise(ウクレレ★パラダイス)」代表・高嶋さんのプロジェクトです。英語や音楽という単体の授業ではなく、包括的なコンテンツで国際的な視野を持った子どもの育成に取り組んでいます。現在、既に三鷹市内の6つの小学校で導入の実績があり、今後は三鷹市をモデルとしてその他多くの市区町村への導入を目指しています。
このプロジェクトを立ち上げる前は10年以上旅行会社に勤めていたという高嶋さん。その中で、ベリーダンスやウクレレを習っている人と一緒に現地に行き、現地の人と交流するなど、「旅と文化」をテーマにしたツアーを企画した経験がありました。実際に、言語が異なっていても音楽を媒介として人との距離を近づけてくれる現場を何度も経験されたそうです。
コロナ禍を経て気づいた弦楽器の魅力
小学校教育に弦楽器を取り入れるというアイデアは、以前から考えていたそうです。「日本の学校教育の音楽は、笛やピアニカなど、単音のメロディーを習うことが多いと思います。和音を習うことにより、誰かの歌と合わせたり、伴奏したりと幅が生まれるので、もう少し和音の教育があっても良いのではないかと思っていました。」と語る高嶋さん。
その後、コロナ禍が訪れ、飛沫感染予防の観点から、子どもたちが合唱したり、笛を吹いたりする授業ができなくなりました。弦楽器であるウクレレは、飛沫の心配もなく音楽を楽しめることが導入のきっかけになりました。また、2019年に発表されたGIGAスクール構想でタブレット学習が一気に普及したことや、2020年から小学3年生での英語教育が必修となったことも、プロジェクトへの追い風になりました。荒川区の小学校への導入事例では、ICT教育の一環としてプロジェクトの実施が決まりました。「子どもたちがタブレットで世界と繋がり、アプリ使ってお互いに質問しあう研究授業をしました。海外の文化を知ることで、日本の良さにも気づくことができると感じます。」と語られました。
「実際に授業をしてみると、子どもたちの気づきやその中から発せられる言葉が興味深く、お互いの学びになる。」と語る高嶋さん。その場で子どもたち同士の交流が生まれるのも魅力だそうで、音楽以外の側面でも多様な学びができるコンテンツになっています。
ウクレレは、自分の世界を広げてくれる“魔法の楽器”
「ウクレレは人生に多くのきっかけを与えてくれる“魔法の楽器”です。ウクレレスクールを始めて26年間経ちますが、全然飽きません。」と笑顔で語る高嶋さん。子どもが扱うことができ、挑戦しやすく、多世代で繋がりやすい、そんな音楽的な魅力がたくさん詰まった楽器。ウクレレをとおして「誰かと一緒に何かをする喜び」を創りたいと、高嶋さんは考えています。「人が一人でできることは限られていると感じます。授業をとおして繋がりを作り、生きることの楽しさを感じ、楽しみの選択肢を増やしたいという想いで取り組んでいます。
このプロジェクトは、2024年度中に10校の導入が決まっています。今後は三鷹市以外の近接地域、そして東京都全域に広げることを目指しています。また、いずれは実際に子どもたちと一緒にハワイに行き、現地の子どもたちと交流し、ボランティアに参加するなどの「文化交流プログラム」の企画も考えているそうです。高嶋さんのモットーは“生活にひとつ彩りを”。「ウクレレを弾いてみたいという人がいれば、すぐに駆けつけます!」と語る姿からは、ウクレレへの愛情と、プロジェクトへの熱い想いが溢れていました。
2022年度 ビジネス部門

最優秀賞
アフターコロナ時代の家庭の悩みをワンストップで解決する ~まなびナビの「窓口」~
まなびナビ合同会社
中河西 慎平 さん
増え続けている不登校児
文部科学省の調査によると、2020年の不登校児は20万人、2021年は25万人と1年で5万人もの不登校児が増えています。多様化する家庭環境や子どもたちが抱える問題が複雑化していることに加え、コロナによる生活環境の変化は子どもたちの学習環境にも大きく影響しています。さまざまな要因で、「学校の学習環境と合わない」と感じる子どもたちが増えている中で、子ども一人ひとりの学習ニーズに対応したいと考えます。
「子どもたちへ新たな学習の機会をつくりたい」という想いで会社を立ち上げた、まなびナビ合同会社代表の中河西慎平(なこうさい しんぺい)さんにお話を伺いました。
教育業界で「勉強すること」の本質を考えた
10年ほど学習塾の教育現場で仕事をされていた中河西さん。そこで見えてきたのは、子どもたちの学習の機会が家庭の収入に影響を受けてしまう現実でした。
学習塾に通うには、個別指導や受験シーズンには、毎月10万円以上の教育費が必要です。費用がかかるため、学びたい子どもたちや学ばせたい家庭のニーズに合わず、学ぶ機会を得ることができない家庭も多く見られます。
そのような中で5年ほど前に、家庭教師として独立しました。家庭教師をしていて見えてきたのが、登校が安定しない子どもたちがいること。学ぶ環境は学校が全てではない。学校以外で子どもたちが学ぶことを楽しめる仕組みを作り、できるだけ多くの子どもたちに対し貴重な学習機会をつくっていきたい。そんな想いで、2021年に「まなびナビ合同会社」を立ち上げました。
オンラインでの学習支援
現在は、オンラインプログラムを中心に、学校での集団生活に馴染めないと感じる子どもに対し、一人ひとりの個性に合わせたペースで「まなびナビ」のカリキュラムを提供しています。「まなびナビ」は、不登校の子どもにフォーカスしただけではなく、学習塾としての利用など、勉強すること自体を楽しめるサービスにしていきたいと考えています。
専門講師による、国語・英語・数学・理科・社会などの学習に加え、施設などに入所している子どもたちへの教育サポートや、一人ひとりが抱える課題に対し、対面での支援もしています。さらには、子どもの課題に向き合う保護者に対し、“お話会”や“交流会”などを開催し、子どもたちを取り巻く環境にも配慮したサービスを展開しています。
中河西さんからのエールです。
学びに対する「前向きな姿勢」が人生をつくる。これがまなびナビの理念です。
何らかの理由で学校に行くことができなくても、それを理由に学ぶことを嫌いになってしまうのはもったいない。
学校以外で一人ひとりに合った、学ぶ環境があれば、どんな子どもたちも自分の力で人生を切り拓いていくことができると信じています。勉強が嫌いでも「学ぶこと」は楽しいことです。ぜひ諦めずに自分の未来を作っていってほしいと思います。

優秀賞
ヒトとワンコがシェアできる「ペット共生食」で真の家族化を支える事業
株式会社 ワンズデイリー
森崎成仁さん
ペットは「飼う」から「共生する」時代へ
かつてはヒトが犬や猫を「飼う」という意味合いが強かった関係性が、近年変わり始めています。
核家族化や、コロナ禍でペットを迎える人が増え、今では多くの人がペットを家族として認識し、家の中で一緒に暮らしています。まさに「ペットの家族化」であり、「ヒト」と「ペット」の関係ではなく、犬も猫も「家族の一員」として共に生きていく大切な存在になっています。
しかし、その一方でペットの食や健康を意識している人はどのくらいいるでしょうか。同じ家族としてペットの健康寿命を守ることは、飼い主の責任だと考えています。
そこで、ヒトとワンコがシェアできる「ペット共生食」事業を展開している、株式会社ワンズデイリーの森崎 成仁(もりさき しげひと)さんにお話を伺いました。
愛犬の不調をきっかけに犬の健康への意識が変わった
森崎さんの愛犬の陸(リク)が2歳になる頃、陸のおなかのあたりに赤い湿疹ができて痒がるようになりました。病院に連れていくと、「食べ物のアレルギーによる湿疹」と診断を受けたそうです。その後、森崎さんは犬の健康について調べ、無添加の手作りごはんを作り始めたところ、みるみるうち陸の湿疹は改善し、元気になっていきました。この出来事をきっかけに、日々の食事がペットに与える影響について考え始め、「ペットも人間と同じように、食が健康をつくる」ことを痛感しました。
森崎さんは、ペット食として販売されている商品のほとんどが「食品」ではなく、「雑貨」として販売されていることを知り、驚きました。そこで、人間の食と健康を扱うフードコーディネーターをしていた奥さんの繭香(まゆか)さんとともに、「犬が安心・安全に食べられるおやつとごはんを提供する事業」を立ち上げ、スタートさせました。
ヒトとワンコがシェアできるおやつ
株式会社ワンズデイリーが提供する「ペット共生食」は「雑貨」ではなく「食品」であり、ヒトと犬にとって安心・安全な食事です。また、犬の健康に寄り添った、身体にやさしく無添加で人間も犬も美味しく食べられることを重要視して作っています。さらに保健所の審査を受け、人間の「食品」として販売できる安全な品質のものだけを製造しているため、人間が食べても美味しく、さらに犬にとっても体にやさしく美味しいおやつです。犬と同じものを食べることに抵抗を感じる人もいるそうですが、「犬の食べもの」、「人間の食べもの」と区別せず、ペットと一緒のおやつで安心できる幸せな時間を過ごしてほしいと考えています。
ペット共生食で文化を変える
ペットは家族の一員として、我が子のように愛情を注いでいきたい存在です。共に暮らし、時には感情を共有して、できるだけ長く一緒に生きていきたいと願う方も多いでしょう。「同じ釜の飯を食う」という言葉のように、ヒトとワンコのどちらにとっても安全で美味しい食事をシェアすることで、ペットの真の家族化を目指し、場所や時間だけでなく心を共にするきっかけとなってほしいと思います。

三鷹発ベンチャー賞
エシカルを三鷹から世界へ
Menary
木住野 舞 さん
赤いリップは女性に自信と美しさを与えます
赤いリップをつけるだけで、背筋がピンと伸びて自然とポジティブな気持ちになります。そしてそれがスイッチとなって、明るい笑顔になり、周りの人にも笑顔が広がります。赤いリップをつけることは、素晴らしいパワーをもっています。
そう語るのは、日本初のプラスチックフリーのエシカルリップを開発したMenary代表の木住野舞(きしの まい)さん。
未経験から起業し、日本初となる商品の開発は苦労の連続。完成までに1年以上を費やして、こだわり貫いた木住野さんの想いには、赤いリップをとおして世界に届けたい、様々なメッセージが込められていました。
海外生活で見えてきた女性としての生き方
海外ボランティアやシンガポールで働いた経験のある木住野さん。木住野さんにとって、読み書きができることや、教育を受けること、そして自分自身が希望する道への選択肢があることは当たり前でした。しかし、海外生活で見えてきたのは、教育格差や人種差別の被害に遭っている女性たちでした。海外の女性の生き方や考え方に触れ、自分自身の生き方について考えさせられたそうです。さらに、シンガポールの勤務先のホテルで人と接するうちに、メイクが与えてくれるパワーにも気づきました。特に赤いリップをつけることで気持ちがポジティブに高められ、自分らしさを表現できることに気づき、化粧品開発を始めるきっかけになったそうです。
日本に帰国し、今後のキャリアプランと向き合い、「女性として私にできること」を考えた時に、これまでの経験から辿り着いた答えは、“女性が前向きになれるきっかけとなるものを作りたい”でした。
未経験から化粧品業界で日本初のリップをつくる
SDGsやエシカルの考え方が少しずつ浸透してきた昨今。しかし今でも、プラスチックによる海洋汚染は深刻で、日本では年間850万トンものプラスチックのごみが海に流れ込んでいるといいます。しかしながら、化粧品の容器の99%がプラスチックを使用しているそうです。環境汚染や動物実験の上で作られた美しさは、果たして本当の美しさと言えるのでしょうか。Menaryの赤リップ「BENI」を作る際、味や質感、サイズ感はもちろんのこと、プラスチックフリーのリップを目指しました。
また、未経験でコネクションもない状態から始まった商品開発は、新しいことへの挑戦の連続でした。日本で口紅が作られる過程では、プラスチックの型枠があり、そこに口紅の原料を入れていくシステムがほとんどです。日本では作られていない容器の形や紙を素材として、共に一から作り上げてくれる企業を見つけることからスタートしました。最初は話しすら聞いてもらえず、化粧品開発への壁の高さを感じました。
時間的にもコスト的にも苦労することはたくさんありましたが、“私が作り上げる意味”を常に考え、決して妥協はせず、300社以上の企業へ提案を重ねた結果、ようやくカタチにしてもらえる企業と出会うことができました。
BENIに込められたメッセージ
Menaryの赤リップ「BENI」のコンセプトは「エシカル×エンパワーメント(自信をつけるという意味)」。赤いリップは自然と女性を内面から輝かせ、自然と“赤いリップをつけている私”になれる。それは、赤いリップがもたらすエンパワーメントの力です。
流行りのメイクで周りと同じになるのではなく、女性たちが本来持っているそれぞれの美しさに自信を与えてくれるのが赤リップ「BENI」です。
ありのままの自分を愛し、自分らしく胸を張って生きていく女性を増やしていきたいと考えています。

